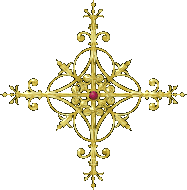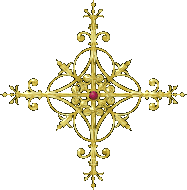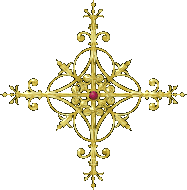

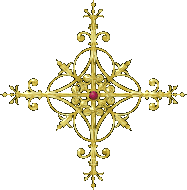
自ら言うだけあってアイオロスの食欲は旺盛だった。
スープを三口で平らげすぐさま肉にかぶりつく。オリーブ油をふんだんに使ったそれをひどく喜び、褒める言葉ももどかしく頬張る。
パンにサラダ、干した果物。次々と手に取り、口に放り込んでいく。
「……」
サガはいつの間にか手を止め、アイオロスをじっと見ていた。
青菜がちぎりもせず押し込められ、白い歯で裂かれていく。唇のオリーブ油は舐め取られ、口の中に消えていく。
力強い咀嚼、忙しく動き続ける顎。包み込まれる野菜、肉、果物。
握られた銀のフォークは食器の上に休止することなくせっせとアイオロスに食べ物を運ぶ。その体温に温められたつややかな柄。
腰かける紫檀の椅子はなめらかな木肌で彼の重さを支える。密着した長い太腿、引き締まった臀部。
足をつけた床、その足を乗せた履き物、身体を包む服------
「サガ」
呼ばれてびくっと目を上げた。
「何をさっきから羨ましそうに見てるんだ? 同じ物を食っているのに」
「あ……ああ」
サガは慌てて手を動かす。味は、わからなかった。
「ジェミニのサガ」
その午後。聖域内をそぞろに歩いていた彼は、覚えのある声に呼び止められた。
「これは教皇」
向き直ってしっかりと正対する。礼を取ろうとするのを、教皇は手で制した。
「何か変わったことはあるか」
「いえ……。本日も市井を回って参りましたが、これといって見受けられませんでした」
「そうか」
教皇は頷いた。
「頼りにしておるぞ、サガ。お前は慈しみ深く進んで救いの手を延べてくれると下々でも大変な人気だ。ましてその力は聖闘士随一だからな」
「……ならば何ゆえ……」
「ん?」
「あ、いえ。時に、アイオロスのことはいつ……」
「皆へのふれか? 来週早々にでもと思っている」
「そう……ですか」
「実はなサガよ。余はその折、粋なはからいをくれてやろうと思っておるのだ」
「と、おっしゃいますと」
「披露目を兼ねる」
「……披露目……!」
くり返した自分の言葉に息が止まった。
「その役目上聖闘士は正式な婚姻は結ばぬ。が、生来の力を血で伝えることは必要だ。それは、存じておろう」
「は、はい……」
胸の中が凍りついていく。
「幸い余の遠縁にふさわしい娘がいる。気だてが良く利発で明るい。何よりたいそう美しい子だ」
「それは……ようございました」
自らの言葉がうつろに響く。全身が空洞のように思えた。
「教皇として勤めるアイオロスの良き支えになるであろう。むろん、お前とは違った意味でな」
「……」
「いずれお前にも似合いの娘を娶せてやるが……ああ、この話、本人には内密にな。明かしたのはお前だけだ」
「光栄です……」